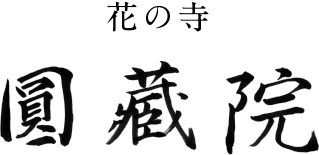2021.06.20 ちいさな法話 仏教と瑜伽(ヨガ)
仏教と瑜伽(yoga)は非常に古い深い結びつきがあります。ヨガ発祥のインドはもちろん、東南アジアの仏教寺院では、ヨガは長時間の瞑想をおこなうまえの準備体操としても実践されています。スポーツではありません。
私が研修をうけたタイ、チェンマイの国際仏教センターでも、タイ式ヨガを全員でおこなうのが日課でした。洞窟のように光の射さないパタヤ(仏間)があり、仏像と灯明だけの静かで仄暗い房で、一日4~6時間の瞑想行をします。その長い長い瞑想のために、ヨガをして心を落ち着かせ、体を整えるのです。
ヨガは「軛(くびき)」、「結びつける」という意味のサンスクリット語「ヨジュ」(yoge)が語源です。精神と身体を結びなおし、バランスをとりもどすのです。西暦200年頃にインドの僧侶哲学者パタンジャリが集成した『瑜伽経』(ヨガ・スートラ)は高野山にも伝えられ、現代でも世界中で読み継がれています。
修行としての瑜伽は瞑想と座法ですが、一般のヨガはプラーナヤーマ(呼吸)とアサナ(ポーズ)を組み合わせて瞑想し、動きながら心身を整えてゆきます。呼吸とポーズを合致させながら、深呼吸で心を穏やかにし、様々なポーズで筋肉と骨格を調整して、体調不良やストレスからも解放してゆきます。
円蔵院の「お寺でyoga」も、講師のYumi先生のご指導で、女性特有のストレスや育児疲れをリリースしながら心身の健康を整えてゆきます。
私がタイの導師から授かった言葉で印象深いのは、「ヨガは、自分の心と体を知って、自分を手放すこと。でも最後は、自分のためではなく、他者のためにヨガすることができるように」とおっしゃれていました。